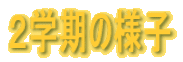
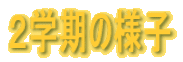
| 9月にすこやかシルバー病院の秋祭りに招待されました。そこで、どんな出し物をするかの話し合いをしました。たくさんの意見が出てきましたが、そのの結果、合唱と打楽器演奏とダンスをすることになりました。翌日から 「合奏チーム」「ダンスチーム」「歌チーム」に分かれて練習開始。どのチームも自分たちで話し合って、発表方法や練習方法を考え取り組みました。そして、9月11日、本番当日−合唱も演奏もダンスも、練習通りばっちりきまりました。お客さんの中には、涙を流してくださった方もいらっしゃり、それを見てじーんと目がうるんでいた子もいました。今回の訪問は学校の都合で30分しかいられませんでしたが、みんな充実した顔をしていました。 また、「もう一度行きたい」と言う子もたくさんいました。今度は、3学期に訪問する予定です。 |
|
| 1学期に、「水道の水はどこからくる?」という学習をしました。それを受け、今度は「使った水はどうなる?」というテーマで学習をしました。使った水は、きれいにする?川に流す?再利用する?という予想を立て、南地区集排センター(アクアパーク)の職員の方に伺いに行きました。そこでは、「排水は全て集排センターに集まってきて、ここできれいな水にする」ということを教えて下さいました。手洗い場の水からトイレの水まですべて集排センターにやってくるというお話には、みんな驚いていました。 施設の見学では、まず汚水のにおいに驚き、どんどん水がきれいになる様子に驚き、最後に浄化された水の中で鯉が泳いでいる様子を見て驚いていました。 |
|
11月27日、越前市にある越前和紙の里(旧今立町)に、紙すき体験と見学をしに行きました。最初に行ったのは、パピルス館。入るとすぐに、職員の方が紙すきの仕方を教えてくださいました。紙をすくときのコツやすき終えた紙に飾りや色を付ける方法などを教わり、いざ実践。紙をすく作業も、飾りや色を付ける作業も、とても楽しそうに行っていました。飾りや色を付けた後は、掃除機みたいな機械で脱水。みるみるうちに、和紙に含まれた水分が抜けていくのをみて、驚いていました。その後、乾燥室も見せてくださいました。熱せられたおおきな鉄板に、みんながすいた紙をはりつけて乾かします。意外な乾かし方を見て、みんな驚いた様子でした。 その次に向かったのは、卯立の工芸館。昔ながらの紙すきを、玉村さんという職人さんが見せてくれました。こうぞ、みつまた等の木からどうやって紙の原料を作るのかや、どんな風に紙をすくのか等を実演や冗談を交え、丁寧に教えてくださいました。 最後に向かったのは、和紙の博物館。12人ぐらいですいたという世界最大の和紙や、とてもきれいな色の和紙、さらには和紙で作ってある人形など、びっくりするような物がたくさんありました。 あっという間に見学時間がすぎ、バスで学校に帰校。自分たちがすいた和紙をもらって、とても満足そうでした。とても楽しい1日になりました。 |
|
 |
 |
| 南の学習で、リサイクル紙すきに挑戦しました。1学期に、リサイクルの勉強で読んだ本の中の「大昔の人は使った紙を集めて、再生し、何度も何度も紙としてつかっていた」ということに習って、紙の再生に挑戦することにしました。 11月30日、第1回目のリサイクル紙すきをしました。再生させるのは、習字で使った半紙。白い部分を丁寧にちぎって、原料を集めました。白い紙をすくには、白い部分だけを細かくちぎることが重要。みんな苦労しながら、細かくちぎって原料集めに取り組みました。その次は煮込む作業。しっかり煮込んで紙を柔らかくします。煮込み終わったら、紙の原料を集めて、たたきます。たたくことで紙の原料を細かくしました。そして、原料を水にとかして、いよいよ紙すき開始。和紙の里で習ったことを思い出しながら、交代交代で何度も紙をすいていました。紙をすくまでの行程が大変だったこともあり、すごく楽しそうに紙すきをしていました。 11月15日は、2回目のリサイクル紙すきに挑戦しました。今回は、調べたことや考えたこと・やりたいことをもとに班分けし、紙すきの仕方を計画しました。1〜3班は前回同様半紙を原料にし、4〜6班は牛乳パックを原料にしました。1・2時間目は、どの班も原料を細かくすることに費やしました。牛乳パックを原料にした班は、初めての試みなので不安げな様子。しかし、細かく切った牛乳パックをミキサーにかけると…牛乳パックがふわふわのパルプ液に変身。見事なパルプ液の完成に、大喜びでした。3時間目ごろからは、どの班もお楽しみの紙すきづくり。どの班も、和紙の里でやったことを思い出しながら、色をつけたり草花をつけたりしていました。色の付け方は、班の個性がでて、色水をつける道具を作った班があったり、レモン・ミカンの皮を使ってにおい付きの色水をつける班があったりしました。 |
|